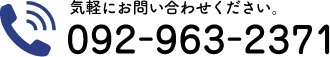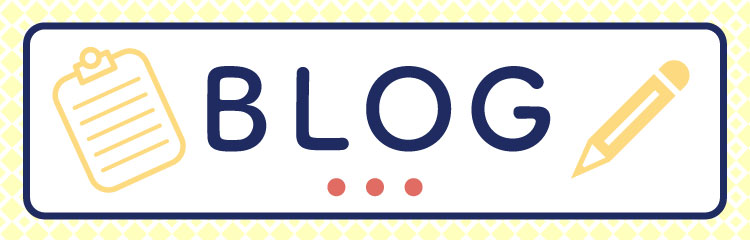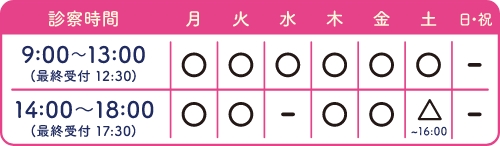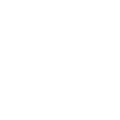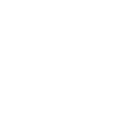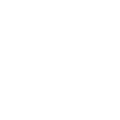福岡県糟屋郡新宮町の脳神経外科「しろうず脳神経外科」頭痛、めまい、もの忘れ、MRI検査
先日我が家に新しい家族が増えました!!
うさぎの”ミミ”です。
ペットショップで抱っこしてみると、その可愛さにとりこになってしまいました。
娘達も妹ができ、メロメロです。
活発で好奇心旺盛なミミちゃん。
これから大切に育てていきたいと思います。


先日長女のハーフ成人式の写真撮影を行いました。
お着物を着てモデルになりきって撮影してもらっているのを見ると、早いものでもう10歳なのかと感慨深いものがありました。
これからも娘らしく成長していくのを楽しみに見守っていきたいと思います。

2024年2月19日(月)につきましては、院長不在のため、代診となります。
2月19日(月) 終日
担当医師:秋山 智明 医師
患者様・ご家族様におかれましては、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解・ご了承を賜りますようお願い申し上げます。
新年あけましておめでとうございます。
2023年10月17日に開業し、早いもので開院して3カ月が経ちました。たくさんの方々のお話を聞くことができて嬉しく思います。
気になっている症状が検査の結果何も異常がないとわかり、ホッとされているのをみるとこちらもよかったなと感じます。
脳神経外科と聞くと脳卒中や脳の手術のイメージが強く、なかなか近寄りにくいものです。(実際私自身が昔までそう思っていました)
そのようなイメージを少しでも払拭するため、当院ではロゴでイルカをモチーフにしています。イルカの聞き取れる周波数は人間の7倍以上もあるといわれています。イルカに負けないように私自身も患者さんの声にできる限り耳を傾けたいと思っています。
大丈夫だと思うけど念のために調べてほしい、こんなことで病院に行っていいのかなということでも、どうぞお気軽にいらしてください。
今年も地域に寄り添う脳のホームドクターとして、皆様が気軽に相談できるようなクリニックを作っていきたいと思っております。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
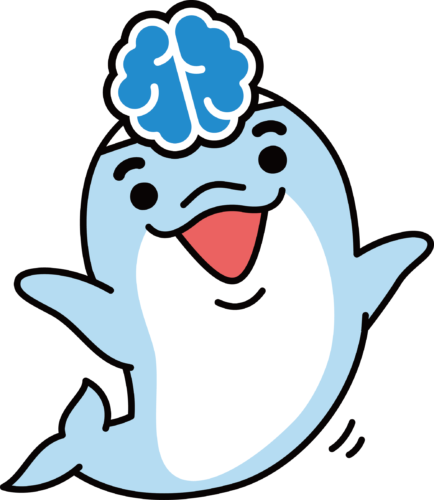
院長 白水 寛理
はじめまして、しろうず脳神経外科院長の白水寛理(しろうずのりとし)です。
開院予定の10月17日がいよいよ後1週間を切りました。
日々、準備を進めるなかで、楽しみと不安が入り混じっています。
BLOGの方では、クリニックの情報をこちらでご報告させていただきます。
加えて、身近に感じてもらうために私自身の日常を時々更新させてもらえればと思います。
不慣れな事が多々あるとは思いますが、よろしくお願いいたします。