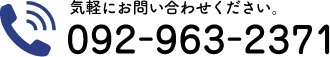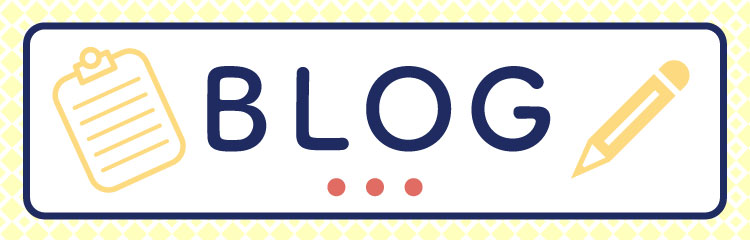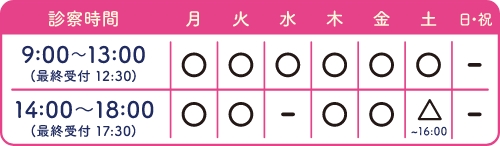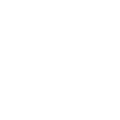福岡県糟屋郡新宮町の脳神経外科「しろうず脳神経外科」頭痛、めまい、もの忘れ、MRI検査
こんにちは、毎日頭痛外来をしている福岡県糟屋郡新宮町の「しろうず脳神経外科」です。
チョコレートって食べすぎるといけないイメージがありますよね?
鼻血が出るよって言われたことがある方もいると思います。
実際にチョコレートの食べ過ぎはダメなんでしょうか?
今回はチョコレートについて詳しく説明していきます。

チョコレートを食べると鼻血が出る?
チョコレートは血行を良くする
そもそも鼻血とはどのように出るのでしょうか?
鼻血の原因の多くは、鼻の穴の入り口から1cmほど入ったところのキーゼルバッハ部位と呼ばれる毛細血管が多く集まった場所が原因となります。
ここは粘膜も薄く、小さな刺激でも血管が切れやすい部位となっています。
チョコレートには、テオブロミンやポリフェノールなど血行をよくする物質が含まれています。
この血行が良くなることで、一時的に毛細血管が刺激されて出血すると言われていますが、医学的な根拠はありません。
鼻血との関連を示す根拠は弱い
チョコレートを食べ過ぎることで鼻血がでると言われるようになった説としてはいくつかあります。
ひとつは、チョコレートのように糖分や脂質が多いものを食べすぎると、体の中に溜まったエネルギーが行き場を失い、鼻血として出るのではないかという説です。
昔はチョコレートが高価な食べ物であったため、子どもたちが食べすぎてしまわないように、たくさん食べると鼻血が出ると母親が注意したという説もあります。
チョコレートを食べ過ぎることのデメリット
脂質や糖質の過剰摂取
チョコレートの食べ過ぎで起こるデメリットの最も多いものとしては、脂質や糖質の過剰摂取による体重増加や、動脈硬化、そして糖尿病のリスクです。
カカオには脂肪分が含まれている他、カカオの苦味を抑える成分として使用されているミルクや砂糖には、脂肪分と糖分が含まれています。
そのため、チョコレートを食べすぎれば、脂質や糖質も多量に摂取してしまうことになります。
脂質は、体を動かすために必要なエネルギーを生み出す役目を持っています。
しかし、過剰に摂取してしまうと、体内に脂肪として蓄えられてしまいます。
結果として、体重の増加の他にも、血液中の中性脂肪及びコレステロールを増加させてしまい、その影響で血管にコレステロールが溜まりやすくなり、動脈硬化につながります。
また、糖分の過剰摂取は、エネルギーを中性脂肪に変えるインスリンの過剰分泌を引き起こし、太りやすくなってしまいます。
さらに糖分の過剰摂取によって糖尿病を発症してしまうと、動脈硬化以外にもさまざまな合併症を招く恐れがあります。
片頭痛との関連
チョコレートのカカオの中にはチラミンという成分が含まれています。
このチラミンは、血管を収縮させた後に拡張させる作用があります。
この時に急激に血流が増えることで、片頭痛と関連して、悪化させる可能性が言われています。

チョコレートのメリット
チョコレートを食べることはデメリットばかりではありません。
リラックス効果
チョコレートのカカオには、交感神経と副交感神経のバランスを調整するセロトニンを増加させるテオブロミンという成分が含まれています。
また、ポリフェノールには、ストレスの軽減に役立つとされており、ストレス増加で分泌されるホルモンの排泄量を抑えます。特にGABA入りチョコレートを摂取することで、忙しくイライラしている時でもリラックス効果や疲労回復といった効果を得ることが期待されます。

女性の脳卒中リスクの低下
チョコレートに含まれるポリフェノールには抗酸化作用があり、コレステロール値の改善、血圧低下などの研究が数多く報告されています。
日本でも研究がなされており、女性ではチョコレートの摂取量が最も多いグループで、最も少ないグループに比べて、脳卒中の発症リスクが16%低く、チョコレートの消費量が週50g増えるごとに、脳卒中のリスクが約14%減少するという報告があります。
生活習慣病に関係する血圧やコレステロールの値が改善するという報告もあり、食べ過ぎずに適量であれば、メリットも多いということがわかります。
間食から摂取するカロリーの目安は1日に200kcalとされています。
ミルクチョコレートであれば、一日に一口サイズで7枚(35g)程度が目安となります。
チョコレートは食べ過ぎると脂質や糖質を過剰に摂取してしまうのでデメリットが大きいですが、毎日少量ずつ摂取することでメリットも多いことがわかります。
適量のチョコレートであれば、身体面でも精神面でもメリットが上回っていきます。

こんにちは、毎日頭痛外来をしている福岡県糟屋郡新宮町の「しろうず脳神経外科」です。
片頭痛が起きているとき、鎮痛薬を内服して痛みを抑えていきます。
しかし、片頭痛が頻回に起きることで生活上の支障をきたすことがあります。
そのような場合には片頭痛を起こさないようにするための予防の治療が必要となります。
片頭痛の予防薬は必要?
片頭痛の発作が月に2回以上、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月に3日以上ある場合は、予防治療を検討します。
副作用が少ない低用量から開始し、2~3カ月程度の時間をかけて効果を判定します。

・抗てんかん薬(バルプロ酸、トピラマート)
バルプロ酸:
抗てんかん薬ですが、片頭痛の予防薬として効果があります。
副作用として眠気があります。
飲み始めが特に眠気を感じやすいですが、継続していくと薬に体が慣れてきます。
500〜600mg/日の内服が勧められます。
トピラマート:
GABAの増強や神経細胞膜を安定させます。わが国では保険適用外です。
・カルシウム拮抗薬(塩酸ロメリジン)
脳血管の収縮抑制、血管透過性の改善効果がみられます。
カルシウム拮抗薬は血圧の薬ですが、塩酸ロメリジンは脳の血管に選択的に作用するため、血圧低下等はみられません。
10mg/日の服用で64.4%、20mg/日の服用で66.7%の患者が効果を実感したと報告されています。
さらに、片頭痛に伴う閃輝暗点や悪心・嘔吐などの前駆症状や随伴症状にも30%程度の改善が認められています。
副作用として徐脈、心不全があります。
・β遮断薬(プロプラノロール)
血管を拡張させることで予防効果がみられます。
血圧や不整脈の薬として使用されており、起立性調節性障害や低血圧の方には慎重投与となります。
心不全、喘息、房室ブロックには禁忌です。
片頭痛の薬であるリザトリプタンとは併用禁忌となっています。
妊娠中の片頭痛予防にも使えます。
30mg/日から開始として30〜60mg/日で調整します。
・抗うつ薬(アミトリプチン)
神経終末におけるノルアドレナリン、セロトニン再取り込みを阻害し、脳内のセロトニン濃度を上昇することで予防します。
副作用として眠気、口渇、便秘があります。
通常うつ病で使用する用量よりも低用量(10〜20mg/日、就寝前)で使用します。
・抗アレルギー薬(シプロヘプタジン)
抗アレルギー薬ではありますが、抗セロトニン作用によって、脳血管の収縮を抑え、頭痛発作の頻度を減少させます。
特に年少者の片頭痛の発作予防に用いられることが多いです。
発作予防の効果が現れるまでに少なくとも1〜2ヶ月はかかります。
・漢方薬
予防薬を飲むことに抵抗がある方は、漢方薬を内服することで片頭痛の予防を行うこともあります。
呉茱萸湯、桂枝人参湯、釣藤散、葛根湯、五苓散などが慢性頭痛に効果があると言われています。

![]()
こんにちは、毎日頭痛外来をしている福岡県糟屋郡新宮町の「しろうず脳神経外科」です。
皆さんは群発頭痛という言葉を知っていますか?
数ヶ月から数年に1度、1-2ヶ月間ほど毎日のように片方の眼がえぐられるほどの激しい頭痛が起こる方は群発頭痛かもしれません。

群発頭痛とは
群発頭痛は慢性頭痛のうちのひとつです。
慢性頭痛としては主に片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛に分かれます。
群発頭痛はこの3つの中でも発症率が特に低い頭痛で、有病率は0.056%から0.4%程度(1000人に1人程度)と報告されています。
特に20-40代の男性で多く見られます。
群発頭痛の症状は、片方の眼の奥がえぐられるような激痛が起こります。
眼の充血、涙や鼻水が止まらないほどの症状を伴うこともあります。
自殺頭痛という別名もあるほどの頭痛で激痛です。
症状は1-2ヶ月間ほど毎日のように起こり、この期間を群発期と呼びます。
群発期が終わると数ヶ月から数年にわたって痛みがない時期が続きます。
群発頭痛はなぜ起きる?
群発頭痛が起こる原因について、はっきりとした理由がまだわかっていません。
いくつかの説が報告されています。
・視床下部説
群発頭痛は夜間に頭痛が起こることから概日リズムの障害が関連していると考えられています。
メラトニンなどの概日リズムを調整するホルモンに異常が生じたり、視床下部という概日リズムを調整する部位の血流が異常亢進することで群発頭痛が起きるとされています。
しかし、実際の頭痛発症時のMRI画像で視床下部の血流が亢進した状態で頭痛が軽快傾向に向かうなどの矛盾点があったり、視床下部を電気刺激して血流を増やすような状態にしたところ頭痛が緩和されるという報告もあることから視床下部を原因とする説の立証は十分ではありません。
・三叉神経と血管との関係説
三叉神経が刺激され血管拡張が起こることが頭痛の原因とする説です。
しかし、これも三叉神経を切除したような状態でも頭痛が生じることや頭痛時の血管拡張が観察できないことから立証は十分ではありません。
・内頸動脈説
内頸動脈やそれが取り囲む海綿静脈洞に炎症が生じるという説です。
しかし、実際に頭痛時にその炎症を証明することが困難であり、立証は不十分です。
・ニューロンネットワークの失調
三叉神経と視床下部までに至る経路の神経伝達物質の流れのネットワークに失調がおこるという説です。
しかし、これもはっきりとした立証はできていません。

いくつか説をあげましたが、どれも立証はできていないため、原因が明らかになっていないのが現状です。
市販薬は効きにくい?
市販薬は基本的に効きません。
多少の痛みは和らぐかもしれませんが、診断がついているのであれば迷わず病院を受診して薬を処方してもらうのが良いでしょう。
群発頭痛の診断と治療
治療は主に2種類あり、群発期の治療と群発頭痛の予防に分かれます。
・群発期
高濃度の酸素吸入が昔から有効とされています。
酸素を吸入することで80%の方で改善が見られたという報告があります。
一番手軽な治療法としてはリドカインという表面麻酔薬をスプレーで鼻粘膜に散布する方法です。
これは30%くらいの方で改善がみられます。
同様の方法として片頭痛で保険適応になっているスマトリプタンの点鼻を発作時に痛い方と反対側の鼻孔にスプレーする方法があります。
また、頭痛発作が激烈な初期の2週間くらいに限り、神経や脳血管の腫れをとる作用を持つ副腎皮質ホルモンを併用することもあります。
・群発頭痛の予防
神経細胞膜の安定化作用のあるベラパミル塩酸塩(ワソラン錠)や、大脳皮質の過敏性を抑える効果のあるバルプロ酸ナトリウム(デパケン錠、セレニカ錠)などを患者さんの症状に合わせて適宜処方します。
できる限り群発頭痛のリスクを下げるためには、アルコールの摂取を控えることが有効です。
また、熱いお風呂やサウナ、辛い食事、激しい運動なども控えましょう。
また、自律神経のバランスを崩さないように毎日できるだけ決まった時間に起床、就寝するなど、規則正しい生活を心がけることが基本となります。
発作が起こりそうになったら、窓を開けて深呼吸を繰り返しましょう。

また、痛むところを冷やすことで多少痛みが和らぎます。
それでも我慢できない場合は、病院を受診しましょう。
群発頭痛は毎日激しい頭痛が来てつらいものです。
くも膜下出血や脳出血なども同様に我慢できないほどの痛みが生じます。
そうした鑑別のためにも、我慢できないような痛みが生じた場合は、一度当院へご相談ください。
![]()